「なぜ日本は“そこまでやる”のか?」―日越チームで生まれた認識ギャップと向き合う
- オフショア開発コンシェルジュ
- 4月15日
- 読了時間: 2分

私たちは、日本とベトナムのチームで協力して開発業務を進めています。その中で、ある対応方針をめぐって認識の違いが浮き彫りになりました。それは、「今すぐ対応すべきか、それとも必要になるまで待つか?」という判断の違いです。
■ リスクへの優先度と判断基準の違い
ある業務判断について、ベトナム側では「リスクの高いものは優先して対応するが、それほど重要ではないものについては、コストを重視し、必要になるまで対応を保留する」といったスタンスが見られました。実際に、他社の事例でも、緊急性が高いものには積極的に対処し、それ以外は最小限の対応で済ませるという考え方が主流のようでした。
ベトナムでは、**「効果的にリスクを下げること」**に重きを置いており、「すべてに対策する」のではなく、「どこに集中すべきか」を判断しているのです。
■ 日本側の考え方:リスクの大小ではなく「備えているかどうか」
一方、日本では、リスクの大小にかかわらず、**「事前にどこまで備えているか」**が重要視される傾向があります。ある程度のコストがかかっても、「もし何か起きた時に、対策していたと言える状態」を保っておくことが、顧客や関係者との信頼関係に直結します。
問題が発生したとき、対策を講じていたという事実が説明責任を果たすための前提になるためです。逆に、対策を取っていなかった場合、たとえそれが些細なことであっても、「なぜ何もしていなかったのか?」と問われる可能性があります。
■ 単なるリスク対応ではなく、考え方そのものの違い
この違いは、セキュリティや業務効率の話に留まりません。日本では「起きてから対応する」より、「起きる前に防ぐこと」に価値を見出す文化があります。これは自然災害など、想定外の事態に対して備えるという国民的な意識とも結びついています。
■ 日本の顧客向け開発に求められる意識
私たちが日本の顧客向けに業務を行う以上、ベトナム側のチームにもその考え方や期待されるレベルを共有する必要があります。「なぜ日本ではそこまでするのか?」を丁寧に説明し、理解を深めてもらうことで、チーム全体の対応力が向上します。
■ 違いを力に変えるために
異なる価値観を持つチームであっても、共通のゴールに向かうためには対話が不可欠です。一方的にルールを押し付けるのではなく、「背景」や「理由」から共有することが、真の理解につながります。
このような対話を積み重ねながら、私たちはより強いチームになっていけると信じています。


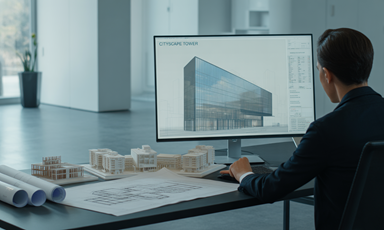

コメント